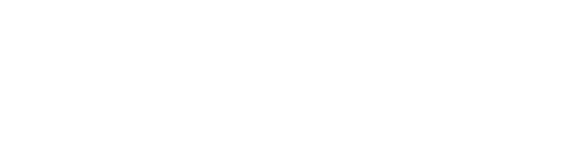
お問い合わせ窓口:明日香村役場
令和7年明日香村議会第1回定例会において、令和7年度の当初予算、並びに諸議案をご審議頂くにあたり、村政運営に関する基本的な考え方と新年度における施策の大綱を申し上げ、議員各位、並びに、村民の皆様のご理解とご協力をお願いするものであります。
さて今世界では、地球温暖化による大雨・洪水・土砂崩れなどの自然災害が続発しています。加えて、この数年、ウクライナやガザ地区への侵攻など、紛争が激化しており、その結果、世界中で資材不足や価格高騰などを引き起こしています。
国内では、バブル崩壊以降、世界でも類を見ないペースで、少子高齢化・労働力人口の減少が起こっており、経済面においては、長期にわたり低成長時代が続いてきました。
このような状況のなか、政府は、物価高、賃金や調達価格の上昇に対応しつつ、デフレを脱却し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を目指して、“物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着"、“地方創生2.0の起動"、“官民連携による投資の拡大"、“防災・減災及び国土強靱化"、“防衛力の抜本的強化"、“充実した少子化・こども政策の着実な実施"など、次々と新たな政策を打ち出してきています。
政府の進める令和7年度一般会計当初予算案の総額は115兆5,415億円で、前年度に比べ2兆9,698億円の増額となっていますが、今後の政府の政策展開によっては、自主財源に乏しい明日香村の財政運営にも大きな影響を受けることが考えられることから、その動向を注意しながら機動的な村政運営に努めることを基調といたします。
本村では、今年1月31日現在、人口 5,038人、高齢化率41.7%となっており、特に、未来の村の担い手づくりである「あすかっこ子育てプロジェクト」や、後期高齢者となりつつある団塊の世代を意識した「トータルケアステーションの検討」、及び、居住する場所の確保を行うための「空き家の活用促進」、並びに、村の農村景観を維持するための「農業の担い手の確保」などの取り組みを加速化していくことが必要となっています。
一方、今年4月13日から始まる関西・大阪万博、そして令和8年夏を目指す「飛鳥・藤原の宮都」の世界文化遺産登録、加えて、地ノ窪地区での宿泊施設の建設など、明日香村をとりまく状況が一変しようとしています。村もこれらと連動して、地域活性化への取り組みをさらに一歩大きく踏み出すことが必要と考えています。
令和7年度の村政運営にあたっては、「第5次明日香村総合計画」に掲げた将来像「『いつまでも住み続けたい』 そう思える夢ある村」「五感で体感できる『明日香まるごと博物館』」の実現に向けて、慎重かつ大胆に取り組みを進めてまいります。
それでは、令和7年度当初予算案の概要について、ご説明いたします。一般会計の予算総額は49億4,100万円で、前年度と比べると、総務費では、システムの標準化対応等のデジタル化推進事業の実施などにより、1億5,571万円、12.9%の増、民生費では、幼保連携型認定こども園建設事業の実施などにより8,158万円、12.4%の増などとなっており、一般会計全体では2億3,700万円、5.0%の増となっております。一般会計と6特別会計、並びに下水道事業会計の合計8会計を合算すると、70億4,463万円となり、前年度と比べると、奈良県広域水道企業団への移行に伴う水道事業会計の減などにより、1億7,010万円、2.4%の減となっております。
それでは、総合計画の3つの基本方針に従い、各種施策を説明させていただきます。
第1は「明日香の暮らし」の分野についてです。
はじめに、子育て支援についてです。幼稚園において、夏休み等の長期休業日に預かり保育を行い、希望する保護者が安心して預けられる環境を提供してまいります。また、幼稚園で開設している“みらいっこルーム"では、様々なイベント等を継続しつつ、子育てに関する学びの場の充実を図ってまいります。
子育て世代の経済的な負担を軽減するため、国の物価高騰対応臨時交付金を活用して、保育所、幼稚園、小・中学校の給食費の無償化を行ってまいります。また、新たに第2子以降の保育料の無償化を実施し、多子世帯の経済的な負担の軽減を行ってまいります。
さらに、親の新たな学び支援事業として、出産や育児のために離職した方などに対し、就職や仕事に役立つ資格や免許を取得するための経費の一部を新たに助成するほか、子育て世帯の定住を目指し、子育て世帯が住宅を新築された際の負担軽減のための助成を引き続き行ってまいります。
一方、少子化対策として、不妊治療の検査対象の範囲を広げるとともに、産後直後から心身のケアや育児サポートを行う、宿泊型の産後ケアの実施を行ってまいります。また、一貫した就学前の教育・保育を受けられるよう「幼保連携型認定こども園」の整備を進めてまいります。
教育においては、引き続き、少人数学級編成等によるきめ細かな授業により、学力の向上と自立した感性豊かな子どもたちの育成を図るとともに、「明日香の風」や「日韓のかけ橋」など、外国文化に触れる機会を通じて、幅広い視野をもったグローバルな人材を育成してまいります。
教育施設等の整備については、児童・生徒の熱中症対策及び災害時の避難所の環境改善をめざし、令和6年度補正予算を利用して、令和7年中に学校の屋内運動場に空調整備を行ってまいります。また、県の公立学校校務支援システムの変更に伴う、情報機器等の更新及びWi-Fi環境の整備を行い、子どもたちの学習環境を整え、セキュリティ強化を図ってまいります。
さらに、国が進める「土日祝の教職員による部活指導の廃止」に対応し、子どもたちの技術力向上のため、「楽スポあすか」などと連携することにより、中学校における部活動の地域移行を進めてまいります。
昨年移転した図書室については、いつでも必要な情報を得ることができる「知の拠点」、並びに、人や情報の交流を生み出す「交流拠点」として、村民の皆様に親しまれる運営に取り組んでまいります。
健康・医療については、奈良県立医科大学と連携し、特定健診に特化した「あすか健康プロジェクト事業」と「健康ステーション事業」を実施するとともに、健康ポイントの対象範囲を拡充させて、健康づくり運動の機運醸成を、より一層図ってまいります。併せて、健診の自己負担額を一律500円に引き下げるとともに、人間ドック受診者の一部自己負担の助成を行い、受診行動の促進を図ります。さらに、がん予防推進員と様々なイベント会場に出向き受診啓発を行い、より一層予防対策を推進してまいります。
次に、介護予防支援については、地域包括支援センターを中心に、社会福祉協議会や関係団体と連携し、高齢者のフレイル予備群の方々に対して体操やサロン活動の支援を行うとともに、買い物やゴミ出し、通院などの生活や移動の支援を実施してまいります。また、高齢者等の交通弱者に対して、赤かめ周遊バスが利用しやすいよう優待乗車証を発行するとともに、デマンド交通を活用した、付き添い型の買い物支援も引き続き実施してまいります。併せて、高齢者等の見守りネットワーク会議を開催し、地域全体で支え合う仕組みを検討し、生活の困りごとに寄り添った支援の整備を図ってまいります。
障がい福祉については、障がいのある人の意思を尊重し、当事者や家族、支援団体のニーズに即した各種福祉サービスの提供を行うとともに、保健・医療等の関係機関と連携した支援体制の確保に努めてまいります。
2025年は、団塊の世代全員が後期高齢者となります。高齢者の取り巻く将来の環境を見据えて、在宅医療と介護の効果的な提供体制のあり方について、令和6年度策定中の基本構想をもとに、これからも住み慣れたところで最後まで暮らすために必要な機能や役割等について、各関係機関と検討しながら基本計画を策定してまいります。
また、医療費助成の中でも子ども医療費については、令和6年8月以降、償還払いではなく現物給付制度を導入しており、病院等受診時の窓口での負担軽減を図っています。
第2に「活力ある村づくり」の分野についてです。
はじめに、公共交通については、赤かめ周遊バスやそれを補完するデマンド型乗合タクシーの運行などにより、誰もが身近に利用できる公共交通を目指して取り組みを進めてまいります。また、来訪者の公共交通利用転換に向けたグリーンスローモビリティやまるごと共通券システムなどの実証、並びに自動運転の実証を引き続き行ってまいります。定住対策としては、空き家バンク制度を効果的に運用し、物件の紹介やリフォームなどの支援を行うことで、居住や働く場所の確保を行ってまいります。
農業の振興については、「農地を守る」という観点から、地域振興公社が主体となり、耕作放棄地の未然防止や農作業受託による高齢農家支援等を行い、耕作放棄地の増加に歯止めをかけ、世界遺産にふさわしい農村景観の維持に努めてまいります。また、県等と連携し、世界遺産構成資産周辺の一体的な景観維持に向けた取り組みを推進してまいります。
次に、「農業者を育てる」の観点からは、引き続き「地域計画」の策定を通じて大字との協議・検討を重ねていき、集落ごとの将来ビジョンを検討するとともに、減少が顕著となっている「農の担い手」については、新規就農者創出に向けた取り組みを継続するとともに、多様な農の担い手確保に向けて農村RMO等の新たな取り組みにも着手してまいります。
さらに、「農業で稼ぐ」の観点から、お米を中心とした農産物のブランド化、市場ニーズを捉えた新規農産物や特産品開発を行い、単価向上による農業生産額の向上を目指してまいります。
村全体の課題となっている有害獣対策については、猟友会と連携し、減数対策として加害個体の特定捕獲と早朝の銃猟を、有害獣多発地域で実施するとともに、捕獲檻の増強や人材確保による駆除の強化も図ってまいります。また、集落診断事業により地域の防御力向上を図るとともに、有害獣の"すみか"となる荒廃した林縁部や荒廃農地において、企業との連携による空間活用型の新たな里山ビジネス等にも取り組んでまいります。
観光振興については、五感で体感できる「明日香まるごと博物館」の実現に向けて、飛鳥観光協会を中心とした村内組織と連携し、インバウンド市場への対応も含めて推進してまいります。また、「飛鳥・藤原」の世界文化遺産登録や関西万博を契機と捉えて、交通事業者等が実施するキャンペーンと連携した観光プロモーション、インスタグラムによる情報発信やプロガイドの育成強化、御朱印企画等を各事業者と連携のうえ、継続して実施してまいります。
また、多様な主体と連携して、冬・夏の閑散期の底上げを目指したキャンペーンを行い、観光シーズンの平準化や新たな客層の誘客促進による質の高い来訪地創出を目指してまいります。
さらに、本村には万葉集に詠われた地名が数多く存在し、全国の万葉故地の中で最も多いとされています。万葉集を編纂したとされる大伴家持のゆかりの地を結んで、令和2年から行われてきた「令和の万葉大茶会」を、今年は飛鳥大会として、第1部大阪・関西万博会場、第2部明日香村へのツアーの形で、2部構成で全国の万葉故地の方々とともに実施します。
世界遺産登録に向けて、外国人を含む来訪者が村内で手軽に情報を発信し取得できるよう、また村内の防犯対策や災害時の通信手段の確保として、Wi-Fi環境の整備を行ってまいります。また、分かりやすい歴史展示に向け、大学連携により、VR空間を活用した歴史展示コンテンツの作成を進めます。
特に飛鳥宮跡から飛鳥寺にかけての周辺地区においては、世界遺産登録とあわせて、どのように“にぎわいの街づくり"を進めていくのか、地域の皆様とともに検討し、実践してまいります。
商工業の振興については、物価高騰の影響を受けた村内事業者及び村民の皆様に対して、村内で使用できるクーポン券を配布し、地域内経済の循環を図ってまいります。
また、今年3月9日の第4回に引き続き、来年第5回飛鳥ハーフマラソンを開催し、スポーツを切り口とした新たな観光客層の開拓、地域経済の活性化、村民の健康意識の向上をめざすとともに、世界文化遺産登録推進と連動し、国内外に広く情報発信を行い、新たな明日香ファンの獲得に努めてまいります。
第3に「明日香らしいたたずまい」の分野についてです。
はじめに、令和7年1月に「飛鳥・藤原の宮都」の世界文化遺産登録に向けた推薦書が日本国政府からユネスコへ正式に提出されました。今年夏頃と想定されるイコモス現地調査の対応など、令和8年の世界文化遺産登録を目指し、協議会のメンバーと協力して取り組みを進めてまいります。
世界遺産の中核をなす飛鳥宮跡及び飛鳥京跡苑地については、古代を感じられる復元整備、公開活用が図れるよう県に働きかけます。高松塚古墳周辺地区においては、文化庁や国土交通省により、修復された古墳壁画の保存管理、公開活用施設が検討されていますが、あわせて中尾山古墳などの史跡整備や園路整備の促進に努めます。酒船石遺跡及びアサガオプロジェクトを行っている牽牛子塚古墳などの史跡地においては、竹林整備などの環境整備を行いながら、さらなる文化観光の推進に繋げてまいります。また、農業振興施設「アグリステーション飛鳥」と連動して、周辺の観光施設や地域資源のネットワーク化を図り、西明日香地域の周遊環境を整えるための取り組みを進めてまいります。
文化芸術の分野では、世界遺産を目指す「飛鳥・藤原の宮都」が、東アジア諸国との積極的な交流により誕生したとされていることから、当時の国際的な交流を示す芸能である「伎楽」を、著名な振付師のプロデュースのもと創作し、公演を目指す「伎楽プロジェクト」を進めてまいります。
また、公民館活動等を展開している各種団体やサークルとともに、次世代を担う子どもたちによる芸能発表を実施するなど、来訪者も含めて多世代にわたる交流ができる“文化が香る村づくり"を展開してまいります。
さらに、長年取り組んできた建築物等への修景補助や集落コミュニティ活動への支援を継続してまいります。加えて、生物多様性の取り組みなども強化してまいります。
これら3つの基本方針の取り組みを支える「社会基盤づくり」としては、まず、道路整備について、国道169号の交差点改良、県道多武峰・見瀬線の島庄地区、並びに主要地方道桜井明日香吉野線の石舞台地区の狭隘部のバイパス整備について、引き続き、県に働きかけを行い、早期完成を目指してまいります。また、既存の集落内の道路については、地元の要望などを踏まえ、緊急度や利用状況などを勘案しながら、自然色舗装などの周辺景観に配慮した整備を順次行い、利用者がより安全・安心・快適に通行できるよう努めてまいります。幹線道路や橋梁については、継続的な定期点検を行い、長寿命化を図るため、計画的に改修や修繕等を行ってまいります。
また、浸水被害が起こっている岡寺参道周辺及び飛鳥駅前広場においては、地域の核となる未来像を描きながら、村民の生命や財産を災害から守るため、地元との浸水対策の計画協議及び災害対策の設計、工事を実施します。令和5年6月の台風2号等で被害を受けた稲渕地区では、再度の被災を防ぐため、土石流対策や急傾斜地崩壊対策事業を進めます。加えて、細川地区では、県営の急傾斜地崩壊対策事業を進めてまいります。
水道事業については、事業統合により令和7年度当初から「奈良県広域水道企業団」として事業を開始します。これからは奈良県と26市町村がひとつとなり、安全で安心・安定した給水を行い、持続可能な水道経営を進めてまいります。
次に、下水道事業については、計画的かつ効果的な調査・修繕等を行うため、マンホールポンプ施設の修繕・改築設計等を行ってきました。令和7年度については、マンホールポンプ施設の改築工事及び昨年度に引き続きマンホール蓋の調査を行ってまいります。
ごみ処理については、引き続き、橿原市に可燃ごみの焼却処理を委託し、適正処理に努めるとともに、その他のごみの減量化、資源化も促進してまいります。し尿処理についても、引き続き橿原市に委託し、適正処理に努めてまいります。
火葬料金については、火葬場が設置されている市町村との火葬料金の格差を軽減するため、火葬料金の一部助成を新たに行ってまいります。
デジタル化の推進については、自治体行政システムの標準化、並びに、「全国どこでも同等の行政システム」による住民サービスを受けられるよう整備を行ってまいります。コンビニ交付事業では、従来の住民票及び印鑑登録証明書の交付に加え、令和7年1月以降は税証明が取得可能となりましたが、今後は、マイナ保険証の利用に加え、令和7年4月からマイナ免許証の利用など、マイナンバーカードを利用したサービスの拡充を行ってまいります。
防災対策については、災害に強い村づくりのため、防災訓練等を通じて自助・共助・公助の意識向上を図るとともに、自主防災組織の活性化や必要な資機材の整備を支援してまいります。また、災害時の迅速な避難行動につながるよう、各大字の自主防災組織や担当地区の民生児童委員の協力により、避難行動要支援者の方々の個別避難計画を作成し、今後、この計画に基づき避難訓練ができるよう検討を進めてまいります。
これらの取り組みによる村づくりを行うためにも、「明日香座」などにより、村民の皆様の様々な提案をお聞きするとともに、大学や企業、そして村に関心を持って活動していただける方々と積極的に連携を行ってまいります。
以上、令和7年度の村政運営に関する基本的な考え方と、新年度における施策の大綱を申し上げました。本方針に基づき、提案させて頂いた令和7年度予算案をはじめ、各議案につきまして、ご審議の程よろしくお願いいたします。

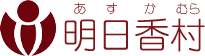
奈良県 明日香村公式ホームページ
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。









